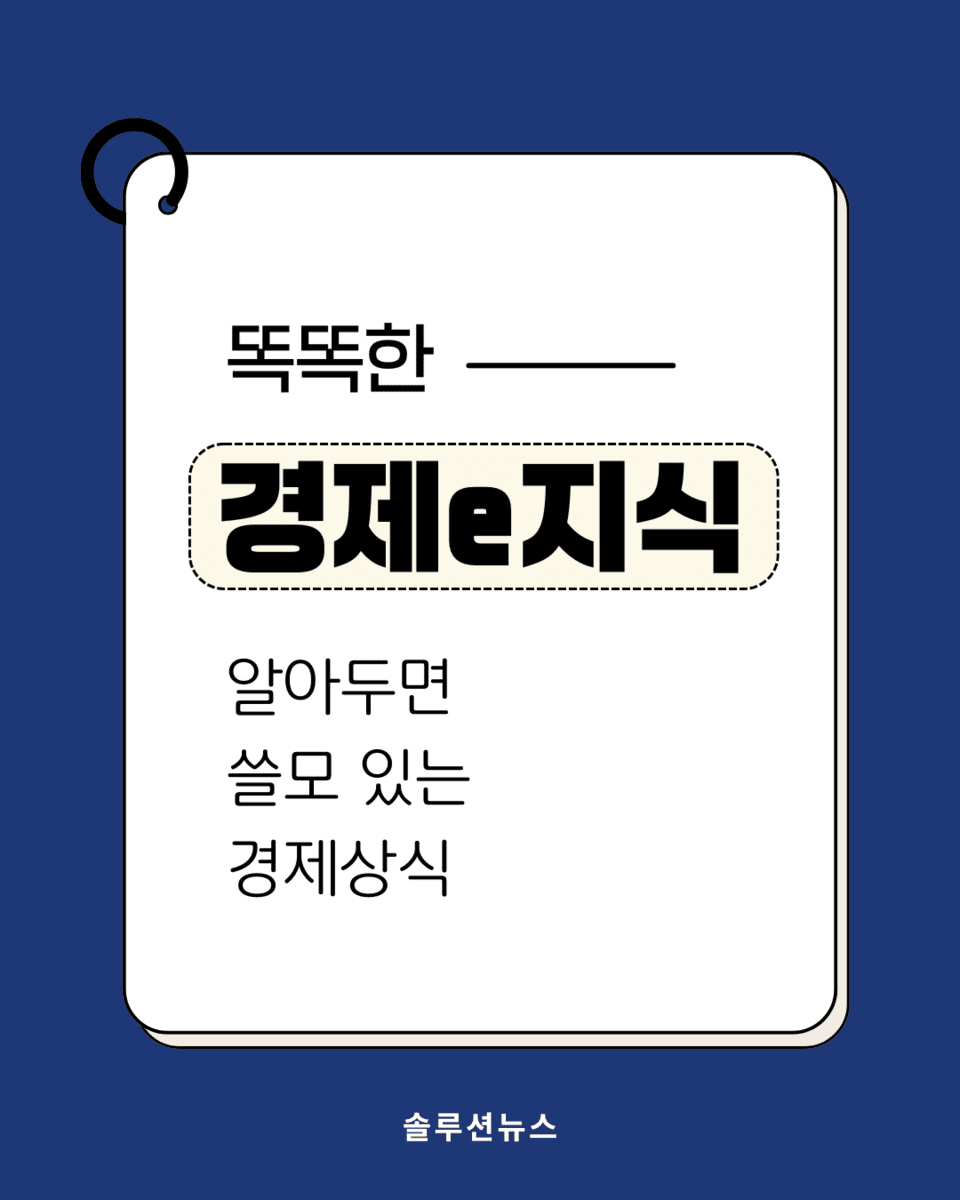レバレッジ(Leverage)は経済と金融で頻繁に使われる用語ですが、未だに多くの人が正確な意味を混同しています。「てこの原理」という意味のように、少ない資本でより大きな資産や収益を創出しようとする戦略です。資金運用、企業経営、個人投資に至るまで幅広く使用されます。
レバレッジは本来、物理学で「てこ」を意味します。小さな力で重い物体を持ち上げることができる原理を借用し、金融では「他人のお金を利用して自分の収益を最大化する構造」を意味します。投資や事業資金の一部だけを自己資本で賄い、残りは借入れなど他人資本を活用してより大きな資産にアクセスすることができます。
例えば、1億円の不動産を購入する際に、自己資本として2,000万円を投入し、残りの8,000万円を銀行ローンで賄うならば、これは5倍(=1億円/2,000万円)のレバレッジを活用したことになります。その不動産の価格が1億2,000万円に上がれば、利益は2,000万円です。投資した自己資本が2,000万円ですので、利益率は100%(=2,000万円/2,000万円×100%)になります。しかし、価格が8,000万円に下がると、資産価値は借入金に等しくなり、自己資本は全額損失となります。
レバレッジは企業でも頻繁に活用されます。特に製造業者や大型インフラ企業のように資本支出が多い場合、初期から大規模な借入を覚悟します。これによって成長機会を確保しますが、外部ショックや金利上昇が重なると危機に陥る可能性があります。グローバル金融危機の際、多くの企業は過度なレバレッジ構造のために倒産しました。
投資市場では、デリバティブ商品やマージントレードなどでレバレッジが一般化しています。個人投資家も株やETF商品で「2倍レバレッジ」や「3倍インバース」など様々な方式で収益を狙います。この商品は基礎資産利益率の2倍、3倍を追従し、利益と損失が同時に拡大されるため、市場予測とリスク管理が重要です。
レバレッジは単なる「借金」ではありません。利益を追求するためのてこです。しかし、基盤が不安定であったり、過度に使用される場合、損失はより致命的になる可能性があります。活用する前に構造を正確に理解し、耐えられる範囲内で使うことが基本です。