生成型AIを上手に使うための鍵は、「どのように質問するか」にあります。
生成型AIは単なる命令処理ツールではなく、入力された文章を分析し、次に来る言葉を予測する確率基盤の言語モデルです。このため、質問の内容、構造、文脈に応じて、成果物の質が大きく異なります。同じ機能を利用しても、一部の人は明確な解答を得たり、また一部の人は不適切な結果に戸惑ったりする理由がここにあります。
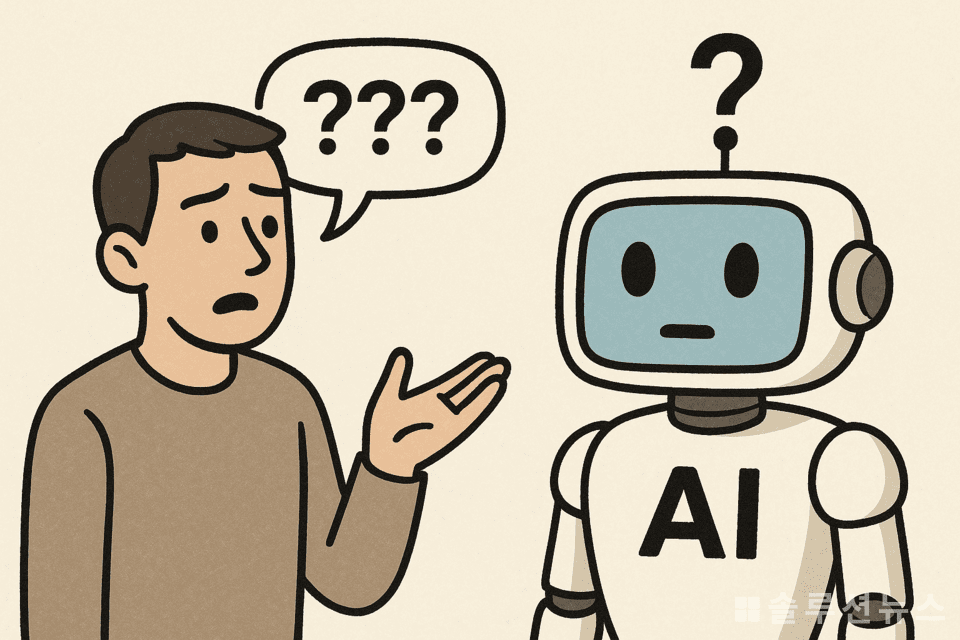
質問は長く具体的であるほどよいです。
多くのユーザーは生成型AIに命令するように質問します。「要約して」「翻訳して」「レポートを書いて」といった指示はおおむね曖昧です。AIは人間の意図を完全に理解できず、文脈、対象、目的が省略された質問には不明瞭な応答が続きます。
より明確な結果を望むならば、文章を構造化する必要があります。テーマ、目的、分量、形式、対象などの核心情報を含めて要求すれば、AIはこれを基により具体的で一貫性のある応答を生成します。例えば「大学生の発表用に、最近の国内電気自動車市場動向を3分の発表分量で要約して」といった具合です。
情報の目的を明示すれば、AIは文体と説明のレベルを適切に調整します。青少年が対象の場合は簡単な単語と簡潔な文章を使い、専門家が対象の場合は用語と統計を強化します。ユーザーが望む成果物を事前に予測して設計してくれるわけです。
複雑な要求は段階的に分けるべきです。
複数の作業を同時に要求する場合、AIは混乱することがあります。「要約して表も作って」のように複合指示が入れば、どの項目から処理するべきかわからないかもしれません。このような場合、要求を分けて入力し、各段階で確認しながら進行する必要があります。
また、最初の応答に満足しない場合でも、直ちに全体の文を変えるよりは、以前の応答を基に部分修正をお願いすることの方が効果的です。例えば「もう少し簡単に要約して」「専門用語を減らして」といったフォローアップ質問を通じて成果物を段階的に精製していく方式です。
生成型AIは会話を記憶し、連続性を維持する機能も持っています。これを活用すれば、長文や複雑な課題も順次分解して効率的に処理できます。
例示提供が応答の質を高めます。
質問に事例を含めると、AIはユーザーが期待する成果物の形をより正確に把握します。「このようなスタイルで書いて」「以下の例のように整理して」のような形です。AIは以前のデータを学習したモデルであるため、類似した形式や文章を参考にすることができる時、応答の一貫性と正確度が高まります。
例は文の構造、語彙、長さ、構成方法に関するモデルの理解を助けます。特に創意的な文書作成や企画書、コンテンツ制作などでは、例示の有無が結果の質を決定します。
質問技術が新たなリテラシーです。
過去の情報獲得は「探す能力」が重要でした。今は「問う能力」がより重要になりました。質問を上手くしないと望む情報を得ることができません。生成型AIはユーザーの要求に応じて自ら成果物を作りますが、基準は全て入力された文にあります。
質問技術は単なる技術ではなく、リテラシーの延長線上にあります。リテラシーとは文章を読み、理解し、活用する能力です。今は書く能力、特に構造化された情報を要求する能力が重要です。
生成型AIを上手く使うために覚えておくべきことはただ一つ。正確な質問が正確な答えを呼ぶという事実です。ユーザーの質問が曖昧であれば、AIはそれに見合った曖昧な答えを出すだけです。
技術は日々進歩していますが、それを扱う手は人間にかかっています。生成型AIも例外ではありません。