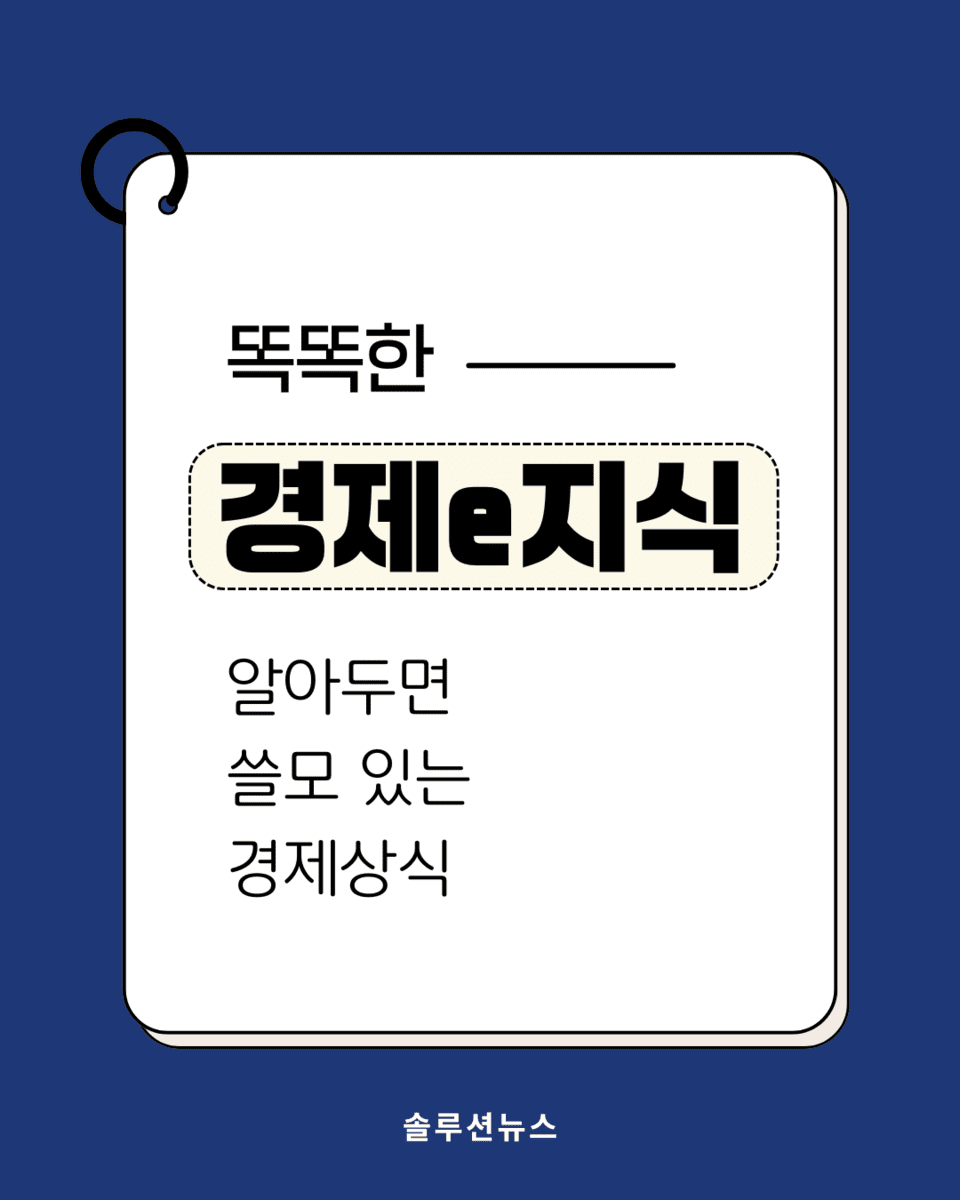ロンドン銀行間金利として知られるリボ金利(LIBOR·London Interbank Offered Rate)は、長い間、世界の金融市場で基準金利としての役割を果たしてきました。銀行が短期資金を相互に貸し借りするときに適用される金利であり、国際金融市場において信用状態と資金の流れを測る尺度として利用されてきました。
リボ金利は1986年に英国銀行家協会(BBA)により公式に導入されました。ロンドン金融市場で主要銀行が提出した金利を平均して算出する形でした。満期別、通貨別に金利が算出され、ドル、ユーロ、円など国際通貨が含まれました。例えば、米国企業がヨーロッパで債券を発行する際、金利は通常リボ金利に一定の加算金利を加える形で決定されました。このため、リボ金利は単なる銀行間貸出金利を超えて、グローバルな債券、デリバティブ、貸出契約など350兆ドル規模の金融商品の基準となりました。
リボ金利は信頼に基づく自己申告方式で運営されました。主要銀行が自身が資金を借りる際に適用されると判断された金利を提出し、それを平均する構造でした。しかし、金融危機後、銀行が恣意的に低い金利を提出し、市場信頼度を歪曲した事実が明らかになりました。2012年には英国バークレイズ、米国シティグループ、スイスUBSなどがリボ金利の操作に関与していたことが判明し、大規模なスキャンダルに発展しました。数十億ドルの罰金と共にリボ金利の信頼性は致命的に損なわれました。
この事件後、各国の規制当局はリボ金利の廃止を推進しました。2021年以降段階的に算出が中止され、2023年6月を機に大部分の通貨と満期で完全に消えました。代替指標としては、米国の場合無担保一晩もの金利のSOFR(Secured Overnight Financing Rate)、英国はSONIA(Sterling Overnight Index Average)、ユーロ圏は€STR(Euro Short-Term Rate)が位置づけられました。これらの金利は実際の取引に基づき算出されるため操作の可能性が低く、金融市場の透明性を高める効果があります。
リボ金利の歴史的な意義は大きいです。国際金融市場が統合される過程で共通の基準として作用し、世界の金融商品価格を決定する核心軸でした。しかし、自己申告式構造が持つ脆弱性が現実化し、金融システムの信頼を崩した事例として残りました。今日、SOFR等の代替指標が定着している中でも、リボ金利が残した教訓は依然として金融市場の警戒心を喚起しています。