中国は2025年9月1日から、すべての人工知能(AI)生成コンテンツに対して義務的に「ラベル」を付けるという強力な規制を施行しました。テキスト、画像、音声、映像だけでなく、バーチャルリアリティコンテンツまで含まれます。利用者が明確に見える「表示ラベル」と、メタデータに隠された「デジタルウォーターマーク」などの非可視的な識別を同時に要求することが主な内容です。
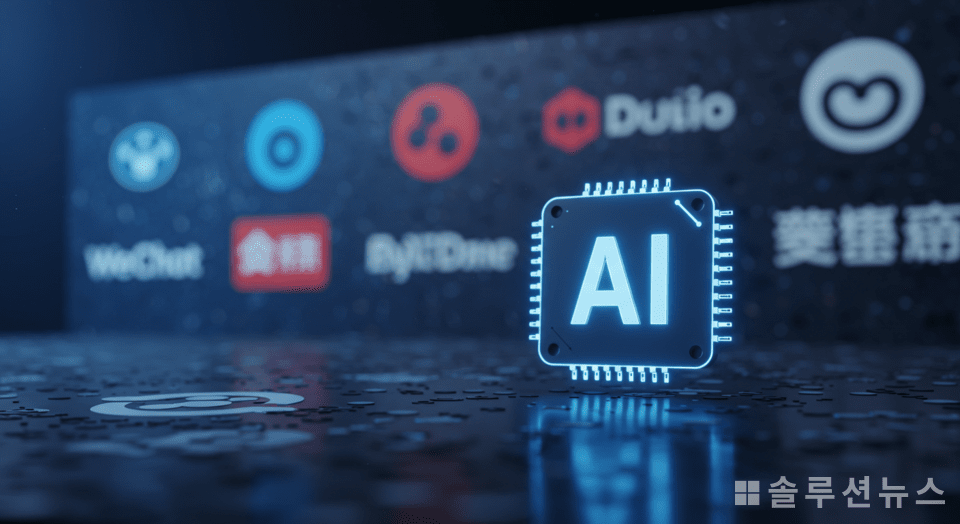
今回の規制は、中国最高インターネット監督機関である国家インターネット情報弁公室(CAC)が、産業情報技術部、公安部、国家ラジオテレビ総局などと共同で用意しました。当局は「AI生成物は虚偽情報、著作権侵害、オンライン詐欺などの社会的リスクを引き起こす可能性がある」として、規制の必要性を強調しました。
中国内の主要ソーシャルメディア企業は迅速に対応しました。テンセントのウィーチャット(WeChat、中国名ウェイシン)は、クリエイターがコンテンツを投稿する際にAI生成かどうかを必ず明記するようにしました。表示しない場合、利用者には「個別の判断が必要」という警告メッセージが表示されます。
バイトダンスが運営するドウイン(Douyin、TikTok中国版)もすべての投稿に見えるラベルを貼るように勧告し、アップロード過程で自動的に出所をメタデータに記録する機能を追加しました。
ウェイボ(Weibo)は「ラベルなしAIコンテンツ」報告機能を新設し、シャオホンシュ(小红书、Xiaohongshu、RedNote)は自主報告がない場合、自らラベルを取り付けることを明らかにしました。
ウィーチャットは月間アクティブユーザー(MAU)が14億人を超え、ドウインは7億6000万人が利用する大規模プラットフォームです。このため、今回の規制施行は中国内のオンラインエコシステム全体に即時的な影響力を発揮することが予想されます。
中国規制当局は特にディープフェイク(deepfake)技術を主要なリスクとして挙げています。AIを活用して人物の顔、音声、行動を操作するディープフェイクは、個人の名誉侵害や社会的混乱、さらには国家安全保障の脅威にまでつながる可能性があるということです。
CACは2025年の清朗(チンラン)キャンペーンの核心課題としてAIコンテンツ管理強化と義務表示制執行を設定しました。該当キャンペーンは毎年オンライン空間の秩序を正すために行われる全国規模の浄化活動です。今年は「偽マーケティング取締り」と「青少年保護」も重点課題に含まれました。
新しい規定はコンテンツ制作者にも大きな変化を要求します。インフルエンサー、電子商取引販売者、マーケティング業者などはAIで作成した文書や映像を投稿する際に必ずラベルを付けなければなりません。これを守らない場合、削除や制裁を受ける可能性があります。
特に画像編集、合成動画制作などでAIツールを多用するエンターテインメントやショッピング分野は直接的な影響を受けます。規制はゲームやメタバースのような「仮想環境」を作るコンテンツにまで拡張され、今後業界全般で新たな作業手続きが必要になりました。
専門家は技術的な困難も指摘しています。AI生成物と人間が作成したコンテンツを自動で区別することがまだ完璧ではないからです。誤って一般の創作物をAIと誤判別したり、逆にAIコンテンツを見逃す場合があります。そのため企業はアップロード前の段階でリアルタイム検出アルゴリズムの開発に投資しています。
今回の規制は欧州連合(EU)の「AI法案」よりも厳しいという評価が出ています。EUは主に利用者がAIコンテンツであることを認識できる「表示」に焦点を合わせましたが、中国はこれに加えてメタデータのウォーターマークまで義務化しました。これは利用者がラベルを任意に削除または操作することを防ぐための装置です。
国際ローファームのホワイト&ケース(White & Case)は報告書で「中国の規制は単純な産業管理の次元を超え、国家安全保障と社会秩序を優先する性格が強い」と分析しています。これは表現の自由委縮への懸念と共に、過度な規制という批判も引き起こしています。
中国の今回の措置は世界最大規模のオンライン人口を抱える市場で適用されるため、国際的な影響力も大きいと見られます。海外のビッグテック企業が中国市場に進出したり協力するには、この規制を必ず満たさなければならないからです。
今後AI技術がさらに高度化する一方で、プラットフォームはより精巧なウォーターマーキング技術を適用することが予想されます。中国内では百度やアリババのようなAI大企業が協力して技術標準を整備する可能性が高いです。
しかし、究極的な成敗は利用者と創作者の参加にかかっています。ラベル義務化を実際に守るか、それとも回避しようとする試みが増えるのかが規制の実効性を左右する要素となるでしょう。