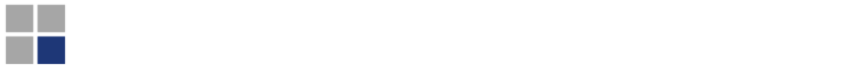人工知能の力を利用した4人に1人 – 有料コンテンツも7倍に急増
生成型人工知能の普及速度が加速しています。国民の4人に1人が生成型人工知能を使用したことがあると答え、テキスト生成だけでなく画像、音楽、音声など多様なコンテンツ生成経験も顕著に増えました。一方、アルゴリズム推薦サービスの客観性に対する信頼は低下し、個人情報の流出への懸念は高まっています。 放送通信委員会(委員長:イ・ジンスク)と情報通信政策研究院(院長:イ・サンギュ)は29日、人工知能(AI)などの知能情報技術とサービスに対する利用者の認識や態度、受容性などを幅広く調査した「2024年知能情報社会利用者パネル調査」結果を発表しました。 主なアンケート結果を見ると、全体の24.0%の回答者が生成型人工知能を使用したことがあると答えました。前年より11.7%ポイント増加した数値で、1年で利用率が約2倍に増加しました。 生成型人工知能の有料購読経験者は全体の7.0%で、昨年の0.9%から7倍以上増えたことがわかりました。 利用形態は多様化しました。テキスト生成が57.2%で最も高かったが、音声・音楽生成が21.4%、画像生成が11.8%と現れました。前年にはテキスト生成が全体の81.0%を占めましたが、今年は他のコンテンツ領域も顕著に増加しました。 生成型人工知能の利用動機 (資料提供:放送通信委員会) 利用の動機は「情報検索効率性」が87.9%で最も高く、「日常業務に役立つ」という回答が70.0%、「会話相手が必要だから」が69.5%でした。該当数値は前年と比較して全般的に上昇しました。 一方、生成型人工知能を利用しない理由としては「知識レベルが高くなければならないと思われて」が65.2%で最も多かった。次いで「個人情報が流出するかもしれないと思われて」が58.9%、「利用が複雑だと思われて」が57.3%と現れました。これは前年と同じ順位でした。 生成型人工知能を利用しない理由 (資料提供:放送通信委員会) 技術の普及に伴う副作用への懸念も提起されました。仕事の代替可能性についての懸念が60.9%で最も高く、創造性の低下(60.4%)、著作権侵害(58.8%)、犯罪悪用の可能性(58.7%)が続きました。 ポータルとYouTubeのアルゴリズム推薦サービスに対する評価は分かれました。「私の趣味に合わせている」と答えたのはポータルが72.1%、YouTubeが71.3%でした。しかし「今後も使い続ける」との回答は、ポータルが64.6%、YouTubeが63.1%で、前年比それぞれ3.7%ポイント、5.4%ポイント下落しました。全体的に満足度と信頼は前年より低下しました。 特にアルゴリズムに対する懸念で最も高い割合を示した項目は、ポータルの場合「不法情報露出」(47.4%)、YouTubeの場合「個人情報流出」(48.2%)でした。昨年最も高かった「価値観の偏向」項目は今年2位に押されました。 利用者はアルゴリズムの運営方式に対する透明性を求めています。「アルゴリズムのコンテンツ選別基準を公開すべき」という回答が69.8%で最も高く、「公共の利益を侵害する場合、制度的補完が必要だ」という回答も63.7%に達しました。すべて前年より上昇した数値です。 知能情報サービス利用経験が最も多い分野は消費(53.9%)、金融(51.7%)、メディア(37.8%)の順でした。昨年より利用率が最も増加した分野はヘルス(37.4%)、医療(19.7%)、金融(51.7%)でした。 知能情報サービス分野別利用経験 (資料提供:放送通信委員会) 今後、知能情報サービスが生活を改善すると期待される分野としては、医療(92.4%)、金融(88.9%)、消費(84.6%)の順に現れました。 知能情報サービス分野別期待水準 (資料提供:放送通信委員会) 今回の調査は「知能情報化基本法」に基づき毎年行われる国家調査で、全国17つの市道で15歳から69歳までのインターネット利用者4,420人を対象に実施されました。 放送通信委員会は「今回の調査結果を詳しく検討し、今後の利用者保護政策を策定する際に活用する予定です。」と明らかにしました。
Read more