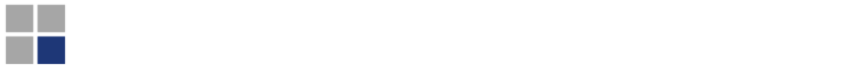城北シニアクラブの「歩行路情報収集専門家」事業が保健福祉部の優秀モデルに選定
ソウル城北区は、城北シニアクラブの「歩行路情報収集専門家」事業団が保健福祉部主催、韓国老人人力開発院主管の「2025年優秀モデルおよび2026年新規アイテム授賞式」で、高齢者雇用優秀モデルに最終選定されたと明らかにしました。 全国27ヶ所の高齢者雇用実施機関が参加する中で、城北シニアクラブ事業団は、交通弱者の歩行環境改善のための活動で革新性を認められ、優秀モデルに選ばれました。 「歩行路情報収集専門家」事業は、城北区内の建物、道路などを撮影し、関連情報をアプリケーションに入力してナビゲーション開発に必要なデータを収集する内容です。視覚障害者、車椅子ユーザーなどの交通弱者が直接参加する方式で運営されます。 参加する高齢者は、データ収集のみならず、活動中に発見した道路の破損などの危険要素を報告するなど、地域社会の安全網機能も果たしています。 성북구청장이 성북시니어클럽의 우수모델 수상을 축하하는 모습 イ・スンロ城北区庁長は「城北シニアクラブの優秀モデル受賞を祝福する」と述べ、「高齢者に適した多様な雇用創出で健康な老後を支援する」と語りました。 ク・ボンギュ城北シニアクラブ館長は「今回の受賞が高齢者雇用に活力を与える契機になることを願う」とし、「今後も高齢者の経験と知識を基に多様な雇用を開発する」と表明しました。 城北区は2025年基準で4,403名の高齢者に雇用を提供しています。城北シニアクラブは専任実施機関として2024年「高齢者雇用および社会活動支援事業」優秀実施機関特別賞を受賞しました。 現在、城北シニアクラブは「歩行路情報収集専門家」、「ハハホホ人形劇」、「料理ノリ体験教室」、「コーヒーガーデン」、「ダモア事業団」など合計1,339名を対象に高齢者雇用事業を運営しています。
Read more